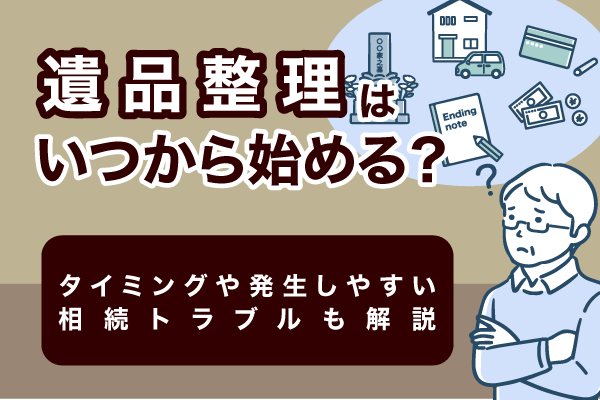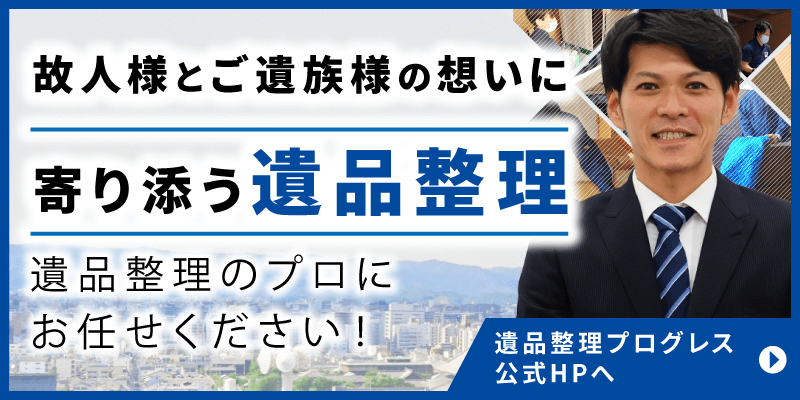遺品整理はいつから始めればいい?
遺品整理のベストなタイミングを知りたい!
遺品整理は亡くなった家族の荷物を片付けるのはもちろん、気持ちを切り替えるために重要なことです。
ですが気持ちの整理がついていない状況で遺品整理をすべきかお困りの人、遺品整理に関するルールやマナーがわからず、タイミングに迷っている人もいるでしょう。
この記事では、遺品整理をいつから始めるかお悩みの方向けに、遺品整理におすすめのタイミングをわかりやすく解説しています。
遺品整理の手順や、親族間で起こりやすいトラブルもまとめているので、遺品整理をスムーズに進める参考にしてください。
遺品整理をいつから始めるか迷っている人におすすめのタイミング

遺品整理をいつから始めるのかお悩みの方は、葬儀の日を基準にして以下のタイミングを選ぶのがおすすめです。
- 葬儀から7日|葬儀が終わった後
- 葬儀から14日|社会保険・役所関連等の手続きを終えた後
- 葬儀から49日|四十九日の法要を終えた後
- 葬儀から3ヶ月|相続放棄の期限を迎える前
- 葬儀から10ヶ月|相続税の申告期限を迎える前
おすすめする理由を詳しくまとめているので、家族や親族と話し合いながら最適なタイミングを選んでみてください。
葬儀から7日|葬儀が終わった後
葬儀後すぐに遺品整理をしたいなら、葬儀から7日以内に開始するのがおすすめです。
故人が亡くなったときには、次のような手続きを行わなければなりませんし、親族が一緒に休みを取れるタイミングでもあります。
- 葬儀の準備(亡くなった後早めに)
- 死亡届の提出(亡くなって1週間以内)
親族と遺品整理について話すタイミングを確保しやすいため、なるべく葬儀に近い日に遺品整理を始めてみてはいかがでしょうか。
早めに遺品整理を終えておけば、故人が住んでいた家の賃料や固定資産税など、継続的にかかるお金の支払いをストップできます。
葬儀から14日|社会保険・役所関連等の手続きを終えた後
葬儀のさなかに遺品整理を始めるのが難しいとお悩みなら、次の手続きを終えた後である葬儀から14日後を選ぶのがおすすめです。
- 社会保険の手続き(健康保険や年金など)
- 資格喪失届の提出
- 死亡届の提出
役所に出向くことはもちろん、年金事務所などを移動しなければならないので、まずは各手続きを終えて時間をつくってから遺品整理を始めるほうが安心でしょう。
家族が初めて亡くなり、手続きに戸惑いそうなら、葬儀から14日後に遺品整理を検討してみてください。
葬儀から49日|四十九日の法要を終えた後
「落ち着いてから遺品整理を始めたい」と考えている人は、葬儀から49日後を選んでみてはいかがでしょうか。
葬儀から49日目には、親族が一堂に集まる「四十九日法要(しじゅうくにちほうよう)」が行われるため、遺品整理について話し合う良いタイミングだと言えます。
仏教の教えを重んじるのなら、四十九日を迎えるまでは故人の魂が現世をさまよっていると考えられているため、四十九日法要でお別れをしてから故人の荷物に手を付けるのが良いでしょう。
親族と一緒に話し合いの時間を確保できることも含め、ゆっくりと遺品整理のことを考えたい人におすすめです。
葬儀から3ヶ月|相続放棄の期限を迎える前
亡くなった家族が残したものが多い場合には、相続放棄の期限である3ヶ月目までに遺品整理を終えておくのがおすすめです。
家族が亡くなった場合、残された品やお金、権利などを3つの方法から選ばなければなりません。
- 単純承認:すべて相続する
- 相続放棄:すべて相続しない
- 限定承認:一部だけ相続する
相続放棄や限定承認を選択した場合には3ヶ月の猶予ができるため、事前に遺品整理を終えて必要な品があるか確認しておくことをおすすめします。
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
引用:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
3ヶ月までに相続放棄を判断する必要があるため、余裕をもって2ヶ月〜2ヶ月半あたりに遺品整理を始めるのがベストです。
葬儀から10ヶ月|相続税の申告期限を迎える前
故人が残したものを相続すると確定しているなら、葬儀から10ヶ月以内に遺品整理をスタートするのがおすすめです。
葬儀から10ヶ月後は相続した遺産のうち、非課税額を超えているものがある場合には相続税を申告します。
具体的な評価総額を把握するためには、遺品整理をして次のような必要書類を見つけなければならないため、10ヶ月以内に遺品整理を終えましょう。
- 銀行通称
- 保険
- 不動産関連の書類
- 貴金属といった価値のある品
10ヶ月以内に申告をしなければならないことから、葬儀から9ヶ月〜9ヶ月半までに動いておくことをおすすめします。
遺品整理は自分の心の整理ができてからでも大丈夫
複数あるタイミングから遺品整理について考えることも良いのですが、特に重要なのは「自分の心の整理」ができてから遺品整理を始めることです。
家族が亡くなって心身ともに疲れてしまうのに、遺品整理のことなど考えられないとお悩みの人も多いでしょう。
遺品整理には具体的なマナーやルールがないため、自分や家族、親族の心の整理ができてから始めても問題ありません。
ただし遺品整理をしないまま時間が経つと、家賃や手続きなどが発生することに注意が必要です。
「心の整理も大切だけど、費用や手間といった負担を増やしたくない」と考えているなら、遺品整理のプロである遺品整理業者に相談してみてはいかがでしょうか。
経験豊富なプロが本人の代わりに遺品整理や片付け、仕分け、買取をまとめて行ってくれます。
遺品整理の仕方・手順
初めての遺品整理で動き方がわからないとお悩みの方向けに、一般的な遺品整理の手順をまとめました。
- 家族や親族と遺品整理のスケジュールや役割分担を話し合う
- 遺言書やエンディングノートを確認する
- 遺品整理を始める前に相続人・親族全員から同意を取る
- 遺品整理を始める(遺品整理業者に依頼する)
- 不用品を処分する
本項で紹介するのは自分たちで遺品整理をする場合の流れです。
遺品整理の仕方がわからないと不安なら、遺品整理業者への相談をおすすめします。
家族や親族と遺品整理のスケジュールや役割分担を話し合う
故人が亡くなった際には、家族や親族など、相続に関わる人たちと遺品整理のスケジュールや役割分担を話し合いましょう。
家族が亡くなった場合には、役所手続きや葬儀業者の手配などを行う必要があるため、すべてひとりで抱え込むのではなく、分担しながら動くのが心身ともに安心です。
関係者と連絡を取る際には、本記事で示した遺品整理のタイミングをもとに「遺品整理の候補日はいつがいい?」「片付けをする際に手伝ってもらえない?」といった相談をしてみてください。
遺言書やエンディングノートを確認する
家族や親族に遺品整理のスケジュールの共有を終えたら、事前に次の重要書類を探して保管しましょう。
- 自筆証書遺言:故人が自分で作成した遺言書
- 公正証書遺言:公証人に作成した遺言書
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在を公証役場で証明してもらう遺言書
- エンディングノート:自分の人生の終末を記したノート
遺言書やエンディングノートには、故人が残した資産がどれくらいなのか、自宅のどこに必要書類がまとまっているのかが記載されています。
遺品整理をスムーズに進める際に役立つ書類ですので、遺品整理をする前に探しておくと良いでしょう。
相続に関する内容がまとめられている場合もあるため、無くさないように大切に保管してください。
遺品整理を始める前に相続人・親族全員から同意を取る
遺品整理をする当日は、すぐ動き出すのではなく事前に参加できなかった関係者に連絡することが大切です。
遺品整理をする際に確認を取っておくことで、後から「そんな話は聞いていない」「自分も参加したい」と言われるトラブルを回避できます。
総務省や法務省でも遺品整理をめぐるトラブルに対して注意喚起が行われているため、トラブル防止のために事前連絡を入れて「〇月〇日に遺品整理をするが問題ないか」と伝えて同意を得ておきましょう。
遺品整理を始める(遺品整理業者に依頼する)
あらかじめ決めておいたスケジュールに合わせて遺品整理を始めましょう。
遺品整理をする際には、次のポイントを意識して動くことが重要です。
- 片付け用のアイテムを準備しておく(ダンボール・軍手、ガムテープなど)
- 仕分用の箱を準備しておく(貴重品・処分品など)
故人の家が広い場合には、関係者ごとに担当する部屋を決めて、分担しながら片付けや仕分けを進めましょう。
遺品整理をする荷物の量が多くお困りなら、遺品整理業者といった片付け・仕分・相続のプロに相談するのもおすすめです。
不用品を処分する
遺品整理の片付けが終わったら、処分品の箱にまとめた品をゴミとして処分しましょう。
処分するゴミの量が多い場合には、自治体の回収サービスを利用するか、ゴミ処理施設への持ち込みが必要です。
不用品の処分が面倒に感じるなら、遺品整理業者への相談をおすすめします。
最終的なゴミの回収・処分まで責任をもって対応してくれるので、ノンストレスで遺品整理を終えられるでしょう。
遺品整理のタイミングは税金・家賃・相続トラブルに気を付けて決めよう
遺品整理で問題やトラブルを起こしたくない人は「税金・家賃・相続トラブル」に注意しましょう。
- 税金:期限を超えると相続できなくなる、追徴課税が発生する
- 家賃:引き払うまで家賃等の支払が続く
- 相続トラブル:事前連絡をしないと裁判沙汰になるかもしれない
始めて家族が亡くなった場合や遺品整理をする場合に発生しやすいポイントですので、気になる項目をチェックしてみてください。
相続放棄や相続税の期限を超えると損をする
遺品整理を長期間放置したままにすると、相続放棄や相続税の申告期限を超えてしまう恐れがあります。
- 相続放棄の期限:故人が亡くなってから3ヶ月以内
- 相続税の申告期限:故人が亡くなってから10ヶ月以内
家庭裁判所で相続放棄の手続きが遅れた場合(3ヶ月を超えた場合)、やむを得ない理由を説明できなければ相続放棄ができなくなります。
借金といったマイナスな遺産を相続する恐れがあるため、早めに遺品整理を始めておくのが安心です。
遺産の相続をするという手続きを終えた後にも、相続税の申告が控えています。
10ヶ月という申告期限を超えた場合、追加で税金を徴収される追徴課税が発生することがあるので十分に注意してください。
亡くなった家族が住んでいる家の家賃がかかり続ける
遺品整理をするまでの期間が開くと、故人が住んでいた家の家賃がかかり続けることに注意が必要です。
近年では賃貸物件で生活する高齢の方が増えていることから、遺品などを引き払うまで継続して家賃を支払わなければなりません。
1ヶ月の家賃が5万円、7万円、10万円だった場合の目安表を以下にまとめました。
| 家賃 | 3ヶ月 | 6ヶ月(半年) | 1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 15万円 | 30万円 | 60万円 | 120万円 |
| 7万円 | 21万円 | 42万円 | 84万円 | 168万円 |
| 10万円 | 30万円 | 60万円 | 120万円 | 240万円 |
遺品整理までの期間、引き払うまでの期間が長くなればなるほど費用が増え続けるため、遺産だけではまかないきれなくなることに注意してください。
勝手に整理すると相続トラブルが起きやすい
遺品整理をする際には、次のような相続トラブルを避けるために必ず親族などの関係者に連絡をしてください。
- 正しく遺品整理されたのかわからないと不平不満が挙がる
- 連絡されないまま遺品整理が進められたと裁判が起きる
親族同士の関係が薄い場合などに、親族間トラブルが発生しやすいと言われています。
遠縁の親族とのトラブルが起きる恐れもあるので、血縁関係者の確認をしたうえで連絡を取ることをおすすめします。
遺品整理ができなくてやばいという人は専門業者に相談しよう
「遺品整理をいつやるかタイミングに悩んでいる」「遺品整理の知識がなく動けそうにない」とお悩みなら、専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。
遺品整理業者といったプロに相談すれば「遺品整理の作業・手続きの手間」をまとめて解消できます。
- 遺品整理のプロが効率よく作業を完了してくれる
- 遺品整理・供養・不用品処分をワンストップで依頼できる
遺品整理の準備に不安をお持ちなら、ぜひ遺品整理業者の魅力をチェックしてみてください。
遺品整理のプロが効率よく作業を完了してくれる
遺品整理業者を利用すれば、大量の荷物があっても最短即日で片付けを終えられます。
経験豊富なプロがスピーディーに作業を進めてくれるため、自身で遺品整理をする必要がありません。
個人に寄り添いつつ丁寧なサポートを提供してもらえるので「自分で遺品整理ができない」と不安な人におすすめです。
遺品整理・供養・不用品処分をワンストップで依頼できる
遺品整理業者に依頼すれば、遺品整理だけでなく次の手続きもワンストップで依頼できます。
- 遺品の供養
- 不用品処分
- 保険の手続き代行
- 自動車や不動産の売買
- 行政手続き
- 家の解体(業者による)
複数の作業をまとめて依頼できるので、葬儀後の手続きに不安をお持ちなら、ぜひ遺品整理業者に相談してみてください。
まとめ
遺品整理をいつやるかお悩みなら、7日、14日、49日、3ヶ月、10ヶ月というタイミングに合わせるのがおすすめです。
遺品整理のタイミングはルールやマナーが決まっていないので、自分や家族の心の整理を終えてから開始しても問題ありません。
もし自分たちで遺品整理ができそうにないとお悩みなら、遺品整理業者といったプロに相談してみてはいかがでしょうか。
本人や親族の代わりに遺品整理や関連する手続きを進行してくれるほか、作業の流れや葬儀後のアドバイスをもらえます。