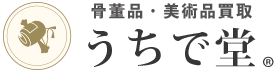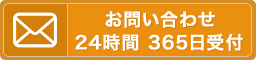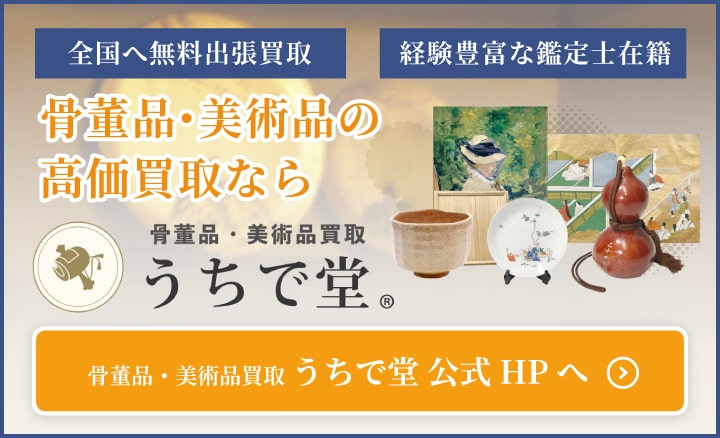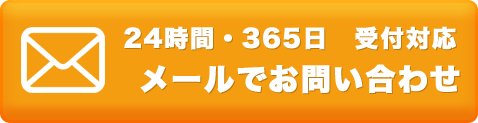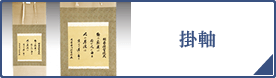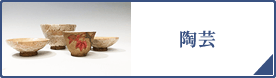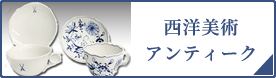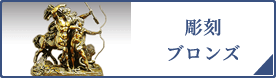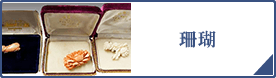骨董品の見分け方教えます!その骨董品本物?偽物?
素人が骨董品の真贋を見極めるのは不可能と断言できます。残念ですがプロの鑑定士と同じレベルで鑑定や査定をして見分けることは到底できません。
しかし、「価値がありそうだから鑑定をしてもらおう」という程度のレベルであれば素人でも骨董品を見分ける方法はあります。ちょっとした特徴やポイントさえ押さえておけばそう難しくはないので、自宅にある骨董品や古い品物で試してみてください。鑑識眼を養えば骨董市やオークションで意外な掘り出し物やお宝を発見できるかもしれませんよ!
骨董品に偽物が多い理由

骨董品の見分け方をお伝えする前に、偽物が市場に出回る理由や仕組みについて簡単に説明しておきます。
偽物を製造しても罪には問われない
まずは日本ではなく、中国の骨董品事情についてお話します。
中国では政府の許可を得ていれば贋作を制作・販売しても罪にならないため、偽物の骨董品を製造している地域が存在しています。つまり、偽物を製造して販売することが容認されているのです。その結果、中国では実に骨董品の約95%が偽物という事態が生じています。
日本も例外ではなく、骨董品の贋作を扱っていたという証明ができない限り、贋作を販売していることを罪には問えません。骨董品は熟練の鑑定士でさえも真贋の判断を間違うことがあり、販売者が「偽物と知らずに販売していた」と主張した場合は販売者側も騙されてしまったということになります。
そのため、購入後に偽物と判明して返金を求めたとしても為す術がないのが実状です。
しかし、鑑定士のようにはいかなくても、ある程度自分で本物と偽物を見極めることができれば自宅にある骨董品の価値を最小限知ることができますし、骨董市やオークションでも納得して品物を購入できるようになるはずです。
そこで次章からは、高額な品物や偽物を見分ける3つの方法を紹介します。
骨董品を売却・購入する際に失敗しないように、見分け方のポイントをしっかりと押さえておきましょう。
骨董品の見分け方①:作者のサインや刻印(落款)を見る

作者のサインや刻印(落款)を見る
本物と偽物を見分ける判断材料で一番分かりやすいのは、制作者の証明となるサインです。
サインは自分の名前を書くだけではなく刻印(落款)が押されている場合もあります。骨董品を納めている共箱や品物の裏側に何かしらのサインがあるか探してください。サイン自体は読めなくてもその有無が重要となります。サインがあれば著名な作家が作成した「作家物」と判断でき、価値が高い品物の可能性があります。
しかし、本物に似せてサインを入れている可能性もあるためサインだけで本物と判断するのはいささか早計かもしれません。十分にご注意ください。
骨董品の見分け方②:年代を確認する

制作された年代を確認する
骨董品は年代が古いものほど高い価値が付きます。古くても現存数が多ければ高価値は期待できませんが、希少性のある骨董品は価値が高い品とみなされます。
一般的な目安として、明治時代以前に生産された品物は価値が高くなる可能性があります。
共箱や鑑定書などの付属品に制作された年代が記載されていることが多いので、確認してみてください。
また、見た目から年代を判断することもできます。
茶道具などの磁器の場合は、古いものほど全体の色合いが薄れて光沢も少なくなります。反対に光沢が十分にあるものは、偽物や贋作、最近になって生産されたものと考えることができます。
骨董品の見分け方③:素材を確認する

骨董品に使われている素材を確認する
現在でもダイヤモンドやエメラルドなどで作られた宝石や品物は価値が高いというのは皆さんもご存知のはず。骨董品も同様に、優れた良い素材を用いて作られたものは高い価値が付きます。
例えば、「金瓶」や「鉄瓶」など金や銀が全体に施されて制作されている品は当然ながら高価値が期待できますが、そのような素材が一部で使用されている骨董品も同じように価値があるものとみなされます。
また、象牙や翡翠(ひすい)などを用いた品は富裕層が芸術品として楽しむために作られた趣向品の可能性が高く、「芸術性」や「希少性」によって高い価値が付きやすくなります。
掛け軸のような日本画系統の場合は見分け方も異なります。古い掛け軸は墨で描かれていますが、偽物や贋作はインクを使用していることがあります。この匂いの違いを感じ取ることができるか否かが、見極める際の重要なポイントになります。
しかし、専門家でもない素人がどの素材を使用しているかを判断して本物か偽物を見抜くのは至難の業です。インターネットで調べたり、専門店に相談したりして情報を収集し、知識の幅を広げて骨董品の世界を少し掘り下げてみましょう。
素材に関する知見を得れば骨董品の見方や接し方が大きく広がるだけでなく、新たな魅力をも発見できるはずです。
品種別の見分け方

骨董品の見分け方を理解したら骨董市に出かけてみましょう!骨董市は全国各地で開催されているので、気軽に骨董品に触れ合えるチャンスです。主だった品種の見分け方を紹介しておきますので、ぜひ実際に足を運んでご自身の目で鑑定してみてください。
①茶碗
景徳鎮
中国第一の陶磁器生産地である景徳鎮(けいとくちん)で生産された陶磁器は、清と明の時代に宮廷御用達の窯・官窯(かんよう)となったものもあり、特に官窯のものは高値で取引される可能性があります。青い染付や、キラキラした粉砕が特徴で、大きいものは日本に入ってきていないので、小さいものを探してみると良いでしょう。
天目茶碗
天目釉と呼ばれる鉄釉をかけて焼かれた陶器茶碗。元や宋の時代に作られていた茶碗で時代の古さと釉薬の乗り具合、時代ごとにミリ単位で決められているサイズの違いが見分けるうえで重要なポイントです。
②根付
根付とは印籠や煙草入れ、革製の小型の袋などを持ち歩くときに紐で帯から吊るすための留め具のことです。江戸時代に爆発的に流行をした、現代でいうストラップのようなものです。骨董品収集家にも人気があり、コレクターも大勢います。素材も象牙や竹製など様々で、作品自体の魅力と作家によって値段に差が大きく開きます。男女の情愛を描いている「春物」、明治初期に海外で流行った「昆虫物」が特に人気があります。
③竹根
竹の根を使った彫り物である竹根(ちっこん)は、竹製品の中でも高値で取引されています。竹製品は保存が困難ですが、良いものは劣化していても高い値段が付きます。
④浮世絵
骨董市でよく出てくるのが浮世絵です。浮世絵の値段は”摺り(すり)”の回数で大きく変わります。赤と青の色の部分が見極めるポイントです。時代が古いものはどんよりと暗い色ですが、時代とともに顔料も進化して鮮やかになります。浮世絵の場合は年号や版元が入っているため制作された年代や時代が見分けやすいですが、偽物や贋作も非常に多く出回っているので注意しましょう。
まとめ
今回は骨董品の見分け方について解説しました。
本物と偽物の骨董品を見分けるのは素人ではほぼ不可能ですが、判断材料となるポイントさえ押さえていれば「これは高く売れるのではないだろうか」という程度までは確信を持てるようになれます。
そのポイントとなるのは以下の3つです。
・作家のサイン
・制作された年代
・使われている素材
ただし、これらは簡易的な見分け方のため表面的な一部分しか確認できませんので、正確な価値の判断は経験と実績が豊富なプロの鑑定士に任せましょう。とはいえ、骨董品への愛着や理解を深めるためには有効な手段となりますので、骨董市などに足を運んで実際に品物を手に取り、鑑識眼を磨いてみてはいかかでしょうか。