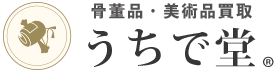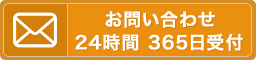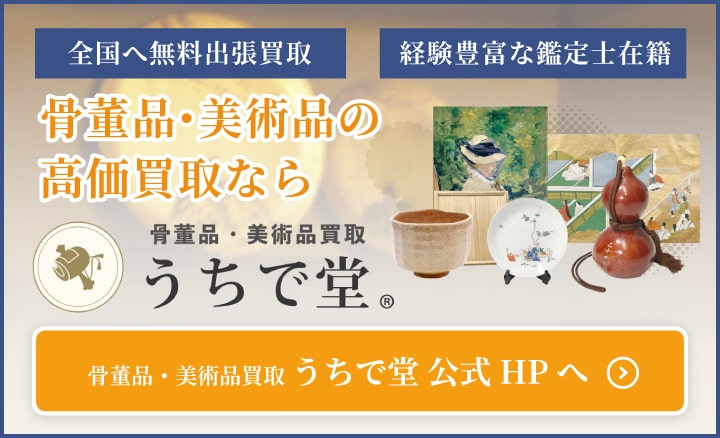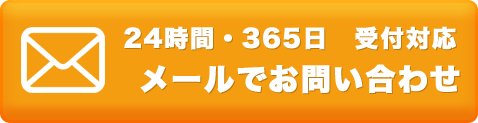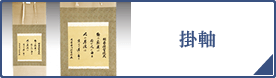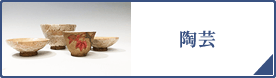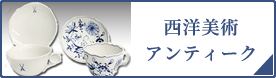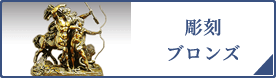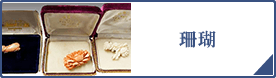骨董品の鑑定書って?売るときはあったほうがいい?
骨董品や古美術品を買取査定に出すときに、一緒に鑑定書も揃えることで買取結果はさらに上がります。有名な芸術家の作品は贋作が大量に流通していることが多く、作品が本物であることを証明してくれる鑑定書が揃っていれば買取側も安心して取引をすることができるためです。
今回は骨董品の価値を保証してくれる鑑定書についてご説明いたします。
鑑定書を作成する理由とは?

骨董品は作家が死亡してから時間が経過するほど、贋作の流通数が多くなります。有名で需要が高い作家の作品であるほど贋作の数は多く、精巧に作られている物もあるため、数々の鑑定経験を積んだ鑑定士でも目利きを誤ってしまうことがあります。
作家や作品に関する専門的知識を持たない人々でも安心して取引が行えるよう、実力のある鑑定機関や専門家によって真作の証である鑑定書が作成されるのです。
鑑定書は原則、既に亡くなった作家の作品のみに作られます。まだ生存している作家の作品の場合、真贋は本人に確認を取るほうが早いためです。
鑑定書は別紙で発行されている物もあれば、シールとして額縁や箱の裏に貼りつけられている場合もあります。
鑑定書を作成する場合の費用はいくら?

一般的には、手数料、鑑定書発行料を併せると1万円から6万円程度の費用が必要になります。
機械を使った精密な鑑定になるほど価格は高騰し、市場価格よりも鑑定書の作成費用が上回ってしまうことは少なくありません。
買取価格では賄えないほどの費用を支払って損をしてしまわないよう、事前に鑑定士へ作品の市場価値を確認しておくことがおすすめです。
作品の市場価値が鑑定代よりも低くなってしまう場合は、無理に鑑定書を作成する必要はありません。
鑑定士は作品の保存状態や希少性から価値を判断しますので、鑑定書がなくても評価が下がることはありません。
鑑定書はどこで作ってもらえる?
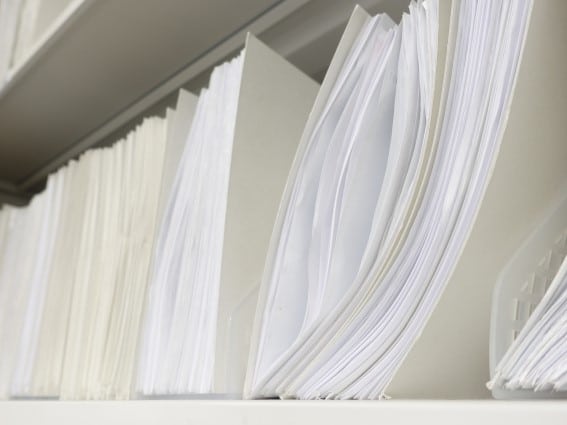
もともと鑑定書が付属していなかった物、鑑定書を紛失してしまった物でも、以下の方法で新しい鑑定書を作成することができます。
作品に精通した鑑定士に依頼する
各作家に精通した鑑定士や、美術市場で信頼されている鑑定機関に鑑定書の作成を依頼しましょう。骨董品の保存状態だけでなく、作家が活動していた時代と作品の様式が合致しているか、作家が用いていた画材と同じであるかどうかを科学的に調べてもらうことができます。
専門鑑定士は作家と血縁関係のある方が多く、子孫や配偶者が亡くなっている場合は鑑定委員会などの機関が運営されていることが多いようです。
販売元に保証書の作成を依頼する
店舗が閉店すると効力を失うため鑑定書と比べると効力は弱いですが、保証書は作品が本物であることを証明してくれる重要な書類です。
デパートや個展で購入した場合は、購入したときの領収書が保証書代わりになりますので、大切に保管しておきましょう。
骨董品買取業者に依頼する
骨董品の買取査定を行っている業者でも、有料で鑑定書を作成してくれる場合があります。
在籍する鑑定士が作成する場合があれば、専門機関へ鑑定を代行する場合もあり、鑑定代行手数料が別途必要になります。
鑑定書作成の総合的な費用は業者によって異なりますので、事前に相談や相見積もりをしてから選ぶようにしましょう。
鑑定書以外にも作品を保証してくれる物はある?

鑑定書がなくても、作品に保証書、共箱、共シールが付属していれば高価買取に繋がる場合があります。
保証書
保証書とは骨董品、美術品を取り扱っている店舗が発行する証明書であり、文字通り販売元が作品の真作を保証してくれるという証明書になります。
骨董品を買取に出す場合、この保証書も鑑定書と同等の価値をもたらしてくれます。
しかし、販売元が閉店、あるいは倒産をしてしまうと作品を保証してくれる店舗が存在しないことになり、保証書の効力が失われてしまいます。
共箱
共箱とは作者が捺印、あるいは署名をした木製の箱のことです。
箱の表側に作品名を記入し、裏側に作者の名前が書いてあることが一般的です。
共箱を紛失してしまった場合に作成してもらえる、鑑定士や鑑定機関が作成した箱書きも存在します。
茶器、工芸品、掛け軸などは共箱に保管されていることが多いです。
共シール
共シールとは主に日本画の裏側に貼り付けられたサインのような物です。
共シールに作品の題名、サイン、落款が記入されていると本物と判断され、作品の価値を高く評価してもらえます。
共シールは作品の裏に貼り付けられた物、作品を入れる額縁に張り付けられた物を二つ揃えて鑑定士に見せる必要があります。
鑑定書付きでも高価買取に至らない場合がある

鑑定書を揃えて買取査定に出したにもかかわらず、高い買取結果を得られない場合があります。
この場合は残念ですが、鑑定書自体が偽造された物、あるいは効力を失っている物だと判定されてしまった可能性が高いです。
鑑定書の中には依頼人から鑑定料を請求するために、作品が贋作でありながら真作と偽って発行された物も存在します。
また、骨董品市場で信頼されている鑑定士や機関が発行した物でなければ鑑定書として認められない場合があるため注意が必要です。
特に横山大観や東郷青児など有名な作家の作品は、所定鑑定機関以外が発行した鑑定書では確かな証拠として判断されません。
有名な鑑定士、機関が作成した鑑定書であっても、鑑定書自体が名を借りて複製された贋作だったことが判明した事例もあります。
複製されやすい物は鑑定書だけでなく、共箱に書かれた箱書きも同様です。
箱書きとは、作品の作者や作成年月日、希少性などを作品を納める箱に記載したものです。
本物であれば鑑定書と同様に作品の価値を高めてくれる大切な付属品ですが、こちらも贋作が大量に出回っています。
人気の作品は詐欺を働く人々の手によって複製され、コレクターに売却することで代金を騙し取る道具として使われているためです。
本物の作品を鑑定士へ持参し、箱書きを作成してもらった後に贋作を中に入れます。本物を所有している限り何度でも贋作と箱書きを複製でき、本物1点を売るよりもはるかに儲けを得ることができます。
そして共箱の素材からも作品の真贋を見極めることができます。
例えば、箱の素材として用いられることが多い桐は江戸時代の中期以降に流通したといわれています。それ以前は杉の箱が用いられていたのですが、何故か桐の箱に収められた江戸時代中期以前の作品が大量に市場で流通しているのです。
ですので、鑑定士は箱書きの情報を鵜呑みにせず、まずは作品を観察して価値を算出します。
このように、鑑定書、保証書が必ずしも真作を保証してくれる書類ではないことを頭に留めておきましょう。
まとめ
鑑定書を揃えることで確かに高い買取結果を得ることができますが、贋作であるにも関わらず作られた鑑定書や、骨董品、美術品市場で認められていない鑑定士や機関が作成した物では査定評価を上げることができません。
また、鑑定書の作成には高い費用が必要となりますので、その作品が鑑定書を作成するべき価値を持っているかを把握してから依頼するほうが良いでしょう。
鑑定書が無くても鑑定を拒まれることはありません。共箱や落款でも骨董品の真贋は判断できますので、鑑定書は真作であることを証明する資料の一つとして捉えておきましょう。