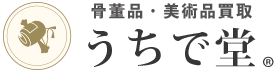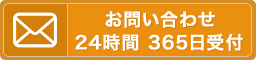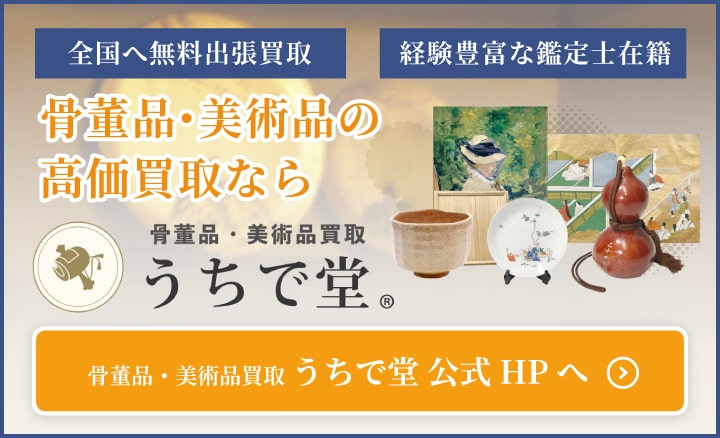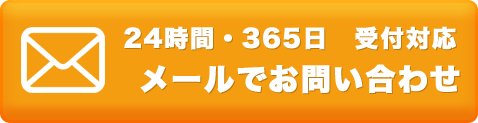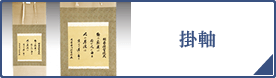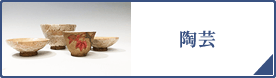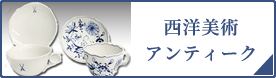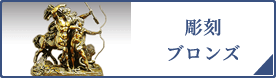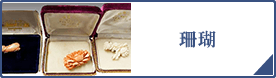骨董品を売る場合に税金はかかる?買取前に知っておくべきこと
家屋の片隅に大量に放置された骨董品。処分に困ったときは買取を検討されることをおすすめします。ただ、買取にあたり注意すべきことがあります。
それが「税金」。骨董品を売却される際に「この品物には税金がかかるのか?」を考慮しなければ、手元に残るお金が想像よりも少なくなってしまった、ということも起こり得ます。
今回は「骨董品を売るとどのように税金がかかるのか?」や、買取前に知っておくべきことを徹底解説します!
骨董品を売ると税金はかかる?

そもそも、前提として骨董品を売るときに税金はかかるのでしょうか。
答えは「国税庁の定める適用条件に応じて、骨董品の売却益に税金がかかる」です。
条件は「買取業者に売却した1組または1点の骨董品が30万円を超える場合」となっています。
ただし、30万円以下で値段が付いた場合は「生活用不動産」として、売却する個数を問わず税金がかかることはありません。
骨董品は個人の保有する資産としてみなされ、買取業者への売却は「譲渡」となるため「譲渡所得税」として課税されることになります。
譲渡所得は、所得税における課税所得の区分の一つとして所得税法に定められています。
骨董品は法律上税金の適用条件を満たすため、基本的に必ず納税しなければなりません。
ただし「生活用不動産の譲渡による所得」は非課税になるという例外もあります。
家具、通勤用の自動車、衣服、タンスなどの「生活用不動産」の譲渡による所得は、課税対象から外れることも法律で定められています。
したがって「生活で不要になった骨董品」は課税され「骨董品として売却できるが生活で使われる物」は課税されないと理解しておきましょう。
ちなみに、骨董品にかかる税金として「相続税」や「贈与税」も存在します。
「相続税」は、相続によって相続人に引き継がれ「相続財産」となった骨董品に対してかかる税金です。
相続で受け取ったものにも税金がかかってしまうので、相続人は引き継ぐ前に税金についてもご遺族と共有しておくとよいでしょう。また「贈与税」は個人に年間110万円を超える物品・金品を贈った場合に課税されます。こちらも然るべきときに備え入念に確認しておきましょう。
どんな種類の骨董品に税金がかかる?

課税対象となる骨董品は以下の通りです。
基本的に全ての骨董品に税金がかかります。
課税される骨董品
絵画、版画、書画、古い機械器具、ブロンズ像、宝石、陶磁器、茶器、茶道具、ブランド品など
これらの買取金額が1個もしくは1組あたり30万円を超えると税金がかかることになります。
ただ、中には実用性の高い茶道具などの美術品に対して「まだ生活で使えるから、税金がかかるのはおかしい」「これは美術品ではない」と主張される方もいらっしゃいます。この場合も、税金が適用される条件を満たした時点で課税されることになります。
売却金額が30万円以下であれば生活に必要な物とみなされるため、非課税対象になります。
また、普段生活で使うと思っていても、年数がかなり経過しているものや、骨董品としての価値があるとみなされたものは課税対象になることがあります。
万が一品物の状態が悪かったり、特殊なつくりにより課税対象か分からない場合は、信頼できる査定士や税理士に相談し判断を仰ぎましょう。
基本的に、骨董品や美術品の買取金額の計算は「財産評価通達」と呼ばれる国税庁が定めた評価方法で「精通者意見評価等を参酌して評価する(鑑定)」と決められています。したがって、迷われた際はプロの力を借りることが推奨されます。
課税金額の計算方法は?

骨董品や美術品の課税金額の計算方法は以下の通りになります。
【譲渡所得の金額】= 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-50万円
「譲渡価格」は査定により最終的に確定した買取金額を、「取得費」は購入代金で、購入手数料や修繕費などを合算した金額を表します。
また「譲渡費用」は品物を売るために直接かかった費用を指します。
例えば、譲渡価格120万円、取得費40万円、譲渡費用が15万円の場合、
120-(40+15)-50=15
で譲渡所得は15万円。つまり15万円に対して税金がかかるということになります。
この最後の50万円は「特別控除」といい、とくに高額な骨董品や美術品を売却される際適用できます。
計算結果がマイナスになれば、課税対象にはなりません。ただし、種類によって控除金額が異なるのと、その年の合計譲渡価格から引き算されるためご注意ください。
ちなみに計算上、売却価格が30万円を超えたら申告が必要になるケースが多く、歴史的価値や希少性が高いものほどその確率が高いといわれています。
したがって、30万円以上の値が付いた場合は年度末に確定申告が必要になるかもしれません。
また「取得費」が不明な場合は、譲渡金額のうち5%を「概算取得費」として計算に入れることができます。
先ほどの例でいくと、譲渡価格の120万円のうち5%となるので
120×0.05=6
つまり、6万円が「概算取得費」となります。
以上が買取金額の基本的な計算方法になります。買取査定は基本的に専門業者や税理士に依頼するのが基本ですが、
ご自身で大まかな金額を計算され、不用品と買取依頼品に分別することで、作業を比較的スムーズに進めることもできます。
どのような買取方法がある?

基本的に「店舗で買取」もしくは「WEB上で買取」の2通りがあります。
近年は、買取を店舗ではなく全てWEB上で手続きするサービスが増えてまいりました。
代表的なものだと「オークションサイト」や「メルカリ」などが挙げられます。
また最近は「転売」と呼ばれる方法で、骨董品や美術品をWEB上で安く仕入れ、買取専用サイトで売却するユーザーも増加してきております。
実際、そのようなWEBサービスで手続きすると、査定金額が数%上がるなど、特典が多いこともあります。ただ取引の内容や価格によって課税となる対象物や金額が異なってくるため、店舗の買取業者と同様、譲渡所得税の申告や納税は必ず行うようにしましょう。
ちなみに、売却にかかった諸費用は「必要経費」として計算することができます。ネットオークションやフリマプリを利用された際の通信費や送料など、各種手数料が該当し、譲渡所得税の節税効果が期待できます。
ただし、自宅で取引を完結させた場合は、申告した金額全てが適用されるわけではないことにご注意ください。
買取にかかる住民税・国民健康保険料は?
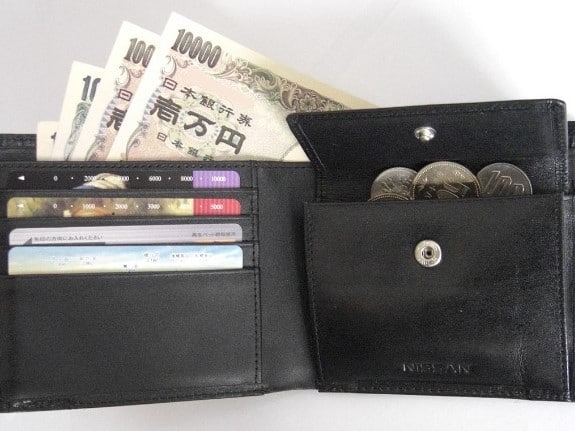
私たちが生きていく上で必ずかかる”生活経費”に「住民税」と「国民健康保険料」があります。どちらも前年の合計所得金額の多寡に応じて算出されます。
前年の所得が多ければ多いほど支払金額は当然増えていきます。価値の高い骨董品価格30万円を超える骨董品の買取などで譲渡所得が生じた際は、支払納付書を見て必要以上に焦らぬよう買取する骨董品の選別や、合計所得金額の計算を入念に行った上で売却しましょう。
まとめ
私たちが普段物を買うときに支払う消費税と同様に、骨董品にもちゃんと税金がかかります。
金額に応じて高い税金を支払うことになるので、どの骨董品にいくら値段が付き、どれくらい課税金額を減らせるのかを事前に知っておくことで、必要最低限の出費で確定申告を済ませることができます。
これを機にぜひ、押し入れの奥に眠る骨董品に値段を付けてあげてみてください。