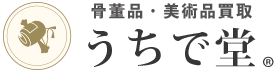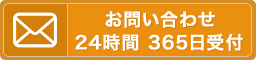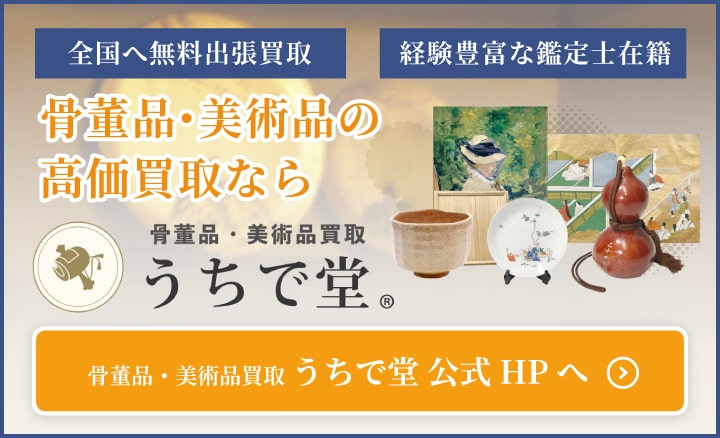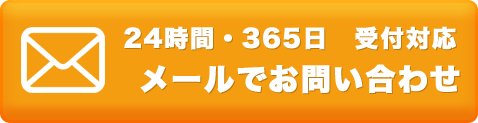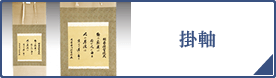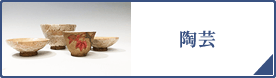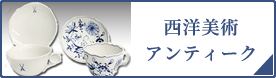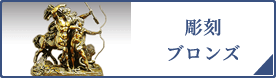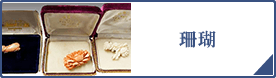骨董品の目利きに必要なこととは?安く買って高く売るポイント
テレビでも時々見かける骨董品の鑑定風景。
「自分も目利きができれば掘り出し物を見つけられるかもしれないのに」「家にあるガラクタが実は価値のあるものかもしれない」と考えたことはありませんか?
今回は「骨董品の目利きになるために必要なこと」、「安く買って高く売るためのポイント」をお話ししていきます。
骨董品とは

現代の日本では、「骨董品」とは古美術品や古道具のことで希少価値のあるものを示す場合が多くなっていますが、全く反対の意味で「古いだけで役に立たないガラクタ」といった意味もあります。
海外ではアンティークと呼ばれ、これは製造されてから100年以上経っている工芸品、美術品のことを指します。
1934年にアメリカ合衆国で制定された通商関税法に「製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品」という文面が記載されており、このアンティークには関税がかからないと明記されています。
この定義がWTO(世界貿易機関)でも採用されていて、加盟国間では100年以上前に作られたものに関しては関税がかかりません。日本もその加盟国の1つです。
ですが、日本の骨董品は必ずしも100年以上経過していないと価値がないわけではありません。
一般的に戦前のものか、戦後のものかで評価されることも多く、戦前のものであれば評価が高くなる場合が多いです。
骨董品の目利きに必要なこと

骨董品の目利き力を養うのは簡単ではありません。
たくさんの本物を見て、時には触れて、経験を積み重ねることで見るべきポイントが分かるようになり、感覚も磨かれていきます。
目利き力を磨くのに有効な方法は主に次の2つです。
その1:本物に触れる機会を増やす
本物が放つ「存在感」「味わい」といった雰囲気や、「手触り」「質感」「色合い」「匂い」といった五感で感じる特徴、これらは実際に何度も見て、触れることでしか覚えられません。
写真や映像では実際のものと色味が違って写ることもあり、重量感や感触などは分かりません。
美術館、博物館、古美術商、骨董品店など本物を実際に見られる場は探せばいろいろあります。
まずはとにかく、たくさんの本物や良品に触れる機会を増やしましょう。
その2:本物と偽物の違いを学ぶ
骨董品について詳しく説明している文献もたくさんあります。
そういった文献を読み込み、本物の特徴をしっかりと学びましょう。
その上で「本物ではないもの」は「本物」とどこが違うのかを比較して、その差を見つけられるようになりましょう。
骨董品は手作りのため、全てが一点ものであり、たとえ同じ作り手が同じように作っても微妙な違いは出てきます。
しかし、たくさん「本物」を見て、経験を積むことで「作風が違う」「筆遣いが違う」「色合いが違う」などの“違い”に気付けるようになってきます。
例えば伊万里焼の場合、キメの細かでなめらかな手触り、透明感のある白い磁肌に呉須で描いた染め付け、赤色・藍色の華やかで繊細、緻密な絵柄が特徴です。
この特徴を知り、「本物」をたくさん見た後で「本物ではないもの」に触れることで、その違いを目で、肌で、感覚で感じ取れるようになってくるのです。
初歩的な骨董品の見分け方
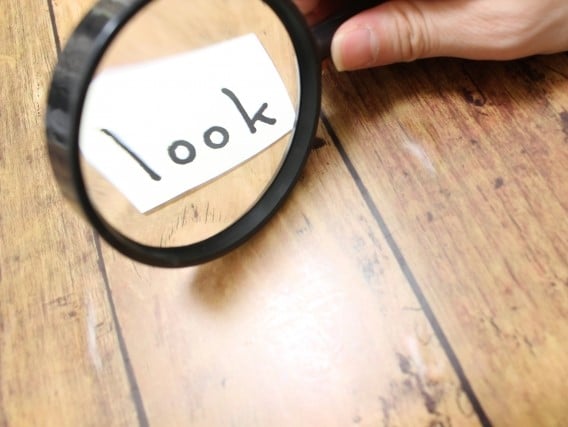
2章で「目利きに必要なこと」をご説明しましたが、「そこまで本格的でなくて良い」「価値の有無がなんとなく分かれば良い」という方もおられるでしょう。
そんな方のために初歩的な骨董品の見分け方を3つお伝えします。
その1:作家の署名、落款、刻印がある
価値のある骨董品かを見分ける方法の1つ目は「作家物」かどうかを確認することです。
「作家物」というのは有名な作家が作成した骨董品のことです。
「作家物」であれば骨董品の裏側やその骨董品を収めている共箱、蓋の裏などにその作家の名前が署名されていたり、刻印などの落款があったりするはずです。
作者自身が「この作品を作ったのは自分である」「この作品は完成品である」という証明のために付けるのがこの落款なのです。
これがあれば「作家物」だということが分かるので、この骨董品に高い価値がある可能性か出てきます。
その2:年代を確認する
価値のある骨董品かを見分ける方法の2つ目は骨董品が作成された年代を確認することです。
年代の古いものほど現存数が少ない場合が多く、数が少なければ希少価値が上がります。
一般的に明治時代以前に作成されたものは価値が高い可能性があります。
いつの時代に作成されたかは付属品や共箱などに書き記されている場合があるので、それを確認しましょう。
その3:骨董品の素材を確認する
価値のある骨董品かを見分ける方法の3つ目は、骨董品の素材を確認することです。
素材自体が高価なものであれば、その骨董品の価値も同じように高くなります。
例えば「宝石珊瑚(とくに血赤珊瑚)」「象牙」「翡翠」「金製品」「銀製品」などは高い価値が付けられます。
骨董品自体が全てこれらの素材で作られていれば間違いなく価値は高いですが、一部分に使われている、という場合でもある程度の価値は期待できます。
上記の「作家物」「素材」「年代」の3つのポイントを確認すればその骨董品にある程度の価値があるかどうか、おおよそ見分けることができます。
ただし、これは本当に初歩的で表面的な部分しか見分けられません。
実際のところ、保存状態が悪かったりすれば価値は下がりますし、精巧に真似て作られた贋作も出回っているので売買を行うという場合には注意してください。
安く買って高く売るポイント

骨董品や美術品だけに限らず、売買で儲けを出すには「安く買って高く売る」ことが大切です。
流行りがあるようなものだと市場価値の変動が激しく、買った時よりも売る時のほうが価値が下がってしまうような場合もありますが、骨董品はそこまで価値の変動が大きくありません。
つまり上手に安値で仕入れることができれば儲けを出すことも可能になります。
そのために気を付けると良いポイントをご説明します。
仕入れのポイント:扱う骨董品のジャンルを絞る
骨董品は「茶道具」「陶器」「陶芸」「絵画」「掛軸」「彫刻」など、そのジャンルは多岐に渡ります。
多くのジャンルを扱おうと思えば、それに伴って必要となる知識も格段に多くなり、広く浅い知識では目利きが難しくなります。
また、買ったものがすぐに売れるわけではないので在庫を抱える物理的なスペースも必要となってきます。
追々、扱うジャンルを増やしていくのは良いと思いますが、はじめはジャンルを絞ってその分野の知識を深めることをおすすめします。
仕入れのポイント:外国の骨董品を扱う
外国の骨董品は、現地では安値で買えて、日本では高く売れるといったものも多くあります。
それを見越して外国から骨董品を輸入し、購入額よりも高く値段を付けて売ることができれば儲けが出ます。
注意点としては、外国の骨董品であればどんなものでも高く売れるわけではないということです。
「どこの国の骨董品が日本で人気なのか」「実際に日本で高値が付いているものはどんなものか」といった事前のリサーチが必要です。
また輸入する際には輸送料などもかかってきますし、骨董品が制作後100年経っていないものであれば関税がかかります。
その辺りも踏まえた上で、購入するものを選びましょう。
販売のポイント:良い状態を保つ
保存状態の良し悪しは販売価格に大きく影響します。
「汚れや傷がない」「色褪せていない」など劣化が少ないほど高値で売ることが期待できます。
かといって、強く磨くと逆に汚れが広がってしまったり、細かな傷ができてしまうこともあるので、繊細に扱うようにしましょう。
簡単に取れない汚れがある場合は、無理に取り除こうとはせず専門家に相談すると良いでしょう。
販売のポイント:付属品を揃える
骨董品を仕入れた際に、共箱や袋、説明書などが付いていた場合には販売のときにもそれらを揃えて売るようにしましょう。
付属品はその骨董品の価値を証明する役割を担っている場合もあり、それらが欠けていると価値を下げてしまうことになりますので注意しましょう。
「安く買って高く売るポイント」を4つ説明しました。
正しい知識を持って骨董品の売買をすることでちゃんと利益を出すことができるのです。
ただ、30万円を超える買取額の高い骨董品の場合、「譲渡所得」の対象となる可能性もあるので気を付けてください。
課税方法も譲渡資産によって変わりますので、判断ができない場合には弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
失敗も大きな糧になる

どんなに優秀で経験豊富な鑑定士でも失敗したことがない人なんて一人もいないでしょう。
それくらい目利きというのは難しいものです。
少し勉強したくらいでは身につくものではありません。
だからこそ、失敗こそが大きな糧になるのだと思って経験を積んでいきましょう。
低価格のものを売買してみる
いきなり高額のものを売買するのはリスクが大きく大変です。
まずは安いものから実際に売買してみましょう。
勉強してきた知識と、本物を見てきた感覚を信じて、自分が「素晴らしい」「良いものだ」と感じるものを購入してみましょう。
家に持ち帰り、落ち着いてじっくりと見たときに改めて気付くこと、見落としてしまっていた部分もあるかもしれません。
次にそれを売ってみる、または無料査定で専門家に見てもらうのも良いでしょう。
自分の目利きが正しかったのかどうかが分かります。
自分が困らない予算の範囲内でこういった売買の経験を積み、実践的な目利きの力を養うことが、後々大きな糧となります。
まとめ
骨董品の目利きになるのは一朝一夕では難しいことですが、古い工芸品からその時代背景や空気感を読み取ることができるのはとても素敵なことです。
経験を積めば骨董品の売買で利益を出すことも夢ではありません。
今回お伝えしたポイントを踏まえて、ぜひ楽しんで挑戦してみてください。