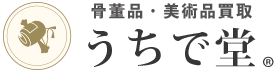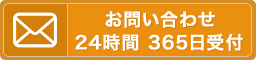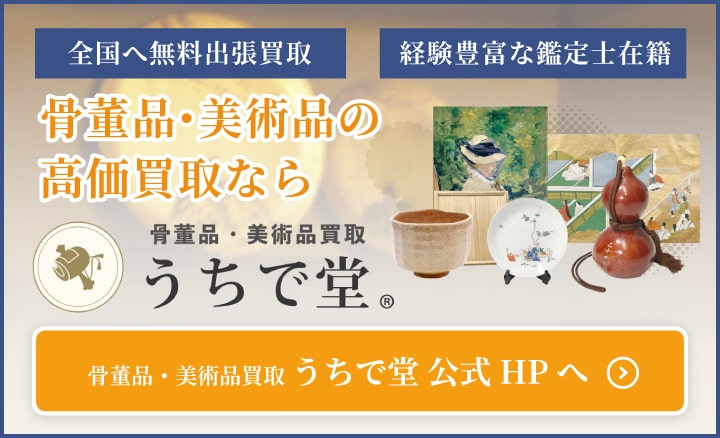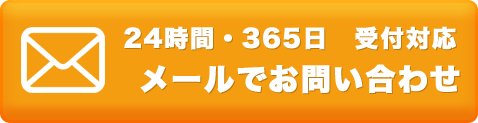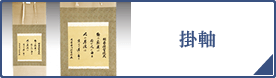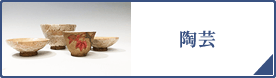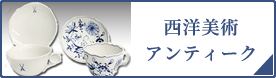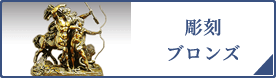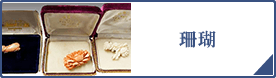骨董品の箱書は価値を見分ける鍵!鑑定前に確認するポイントを紹介!
骨董品が収められている箱は単なる収納箱ではありません。それ自体にも高い価値があるのです。
箱書とは

陶器・茶道具・書画など価値ある骨董品は桐や杉でできた箱に収納され、作成された年代から現代まで大切に保管されてきました。この箱を共箱(きょうばこ)、そしてこの箱に記された作家の名前や銘、製作年などを箱書(はこがき)と呼びます。
この箱書は作品の真贋を見極める材料になるだけではなく、品物自体の価値を保証する働きもあります。
骨董品における箱書の重要性と効果

骨董品の鑑定を行う上で共箱・箱書は非常に重要な役割を担うだけではなく、共箱自体にも価値が認められることが多いです。
由緒ある箱書の効果
基本的には骨董品と共箱はセットであり互いに離れ離れになることはないため、箱書を見ればその中身が判断できるといわれることもあります。そのため、作者本人かその親族、もしくは鑑定人によって施された由緒ある箱書があることは、品物の希少性・真贋を裏付け、価値を保証する意味もあります。
作成年代の特定
共箱の素材は桐製が主流です。しかし、これがポピュラーになったのは江戸時代中期であり、それ以前の江戸時代前~中期ごろには杉の箱が多く用いられていました。そこから逆算して共箱の素材から大まかな作成年代を把握、また、桐製の共箱に江戸時代前期に活躍した作家の作品が収められているようなちぐはぐな状態の贋作の看破などにも役立ちます。
査定額が高くなる
箱書が施された共箱はそれ自体に価値があるため、買取査定の結果も箱書の真贋、さらに言えば共箱の有無で大きく左右されます。
鑑定前の下調べに役立つ
遺品整理や実家の解体に伴う大掃除などのタイミングで大量の骨董品を発見して対処に困ってしまう……というのはよくあるケースです。価値ある骨董品か単なる古物かを専門知識無しで見分けるのはほぼ不可能ですが、箱書の有無でおおよその品物の種類や価値を見分けることはできます。
ただし、箱書にも種類があり(後述)誰が記したものかによって価値は大きく左右されます。さらに、中の品物や箱書が偽物ではないという保証はできないので、鑑定前にこの品にどのくらいの価値があるのかある程度の目星を付けて、せっかくの貴重品を安価で買い叩かれてしまうことの予防策くらいに考えておき、あとは信頼できる鑑定士に任せるのがおすすめです。
箱書の種類

骨董品を収納する箱は、箱書を書いた人物によって大まかに4種類に分類できます。
共箱
作者自身の手で銘・作成年・作家名が記された箱は、作品を作ったときに共に用意した箱という意味を込めて「共箱」と呼ばれます。先述した通り、共箱は中の品と密接な関係にありますので、紛失もしくは、すり替えによって中身と一致しない場合は価値が大きく下がってしまいます。
極箱
鑑定によって中の品物が「本物である」と分かり、鑑定士や鑑定団体、作家の後継者や遺族が証明として書いたものは極箱といいます。有識者が本物であると判断して記すものなので、共箱と同等に品物の価値を証明する材料として扱われます。
書付箱
高僧・大名などが書き付けた所有の記録・日付や茶道の家元などの権威ある人物が箱書を記した場合は書付箱と呼ばれます。
合箱
共箱のような本来の箱ではなく、類似した別の箱に収納されている場合は共箱ではなく合箱(あわせばこ)と呼びます。こちらの場合は中身の品質や出自を保証する効果はありません。
箱書の危険性

ここまで読んでいただければ分かる通り、箱書の存在は品物の価値や希少性を証明する効果がありますが、早合点して失敗したり、それを逆手に取った詐欺に巻き込まれたりする可能性があるなど、リスクがあることも覚えておいて損はありません。
早合点の材料になる
箱書は箱(蓋)の内側、側面、底面のいずれかに書かれており、特に底面は知識がないと見落とす可能性も高いです。その結果貴重な品を安く売り飛ばしてしまったり、悪い場合には廃棄してしまったりすることも考えられます。また、箱書は独特の書体で書かれているため、大して価値のない品を有名作家の作品と見違え、その結果としてその品物にはありえない高額買取を目指して時間を無駄にしてしまうなど、不慣れな箱書の調査で早合点して失敗するケースは多く考えられます。
箱書を台無しにしてしまう
汚れた手で箱書部分に触って汚してしまったり、書付部分をなぞってにじませてしまったりすれば取り返しがつきません。扱いを知らない方だけではなく、不慣れもしくはずさんな仕事をしている鑑定士が無遠慮に触った結果このような事態が起こってしまうことも考えられますので、取り扱いと鑑定を依頼する業者は慎重に選ぶ必要があります。
先述したのは骨董品を売却する際の危険性ですが、買う際にも注意すべき点は多いです。
近年骨董品の贋作(ニセモノ)の作成技術は高まっており、精巧な作りの贋作が法の目を潜り抜けて市場を流通しています。そのため、共箱の中身と箱書が一致しているからといって本物であると太鼓判を押すのは早計といえます。
偽の共箱を掴まされる
共箱とそこに記されている箱書は知識無しでは著名人が記入した共箱か、単なる記録である書付箱なのかを正確に見分けるのは難しいです。そのため、オークションなどしっかりと確認ができない状況で「書いてあるから」と少ない判断材料をもとに買ったり、骨董市などで口車に乗せられて正常な判断材料を失った状態で購入したりしないなど、箱書に判断を任せすぎないよう気を付けるべきケースは多いです。
贋作を掴まされる
骨董品を買う際にも共箱と箱書にのみ注目した結果贋作を掴まされるケースがあります。
例として1件ご紹介すると、共箱自体は極書された本物であり、中身だけが贋作にすり替えられているケースが挙げられます。本物の骨董品が一つあれば有識者に極書してもらうことによって中身を保証できるので中身は精巧な贋作にすり替えておき、手元に残った本物の品を再び極書してもらい……というロジックです。
箱書をもとに鑑定してもらおう

箱書は骨董品の価値を判断する材料になりますが、それだけに捉われると足元をすくわれる原因にもなります。そのため、箱書はあくまで鑑定に出す品や手元に残す品を選ぶための目安・判断材料として捉え、必要があれば信頼できる鑑定士に依頼して鑑定してもらうようにしましょう。
信頼できる鑑定士とは?
「信頼できる」というのは「品物に秘められた歴史的な価値を正確に把握して確実な目利きを行ってくれる」「包み隠さず正確な情報を伝えてくれる」という意味です。前者は一般人では感じられない触感などの特徴を経験と実績から感じ取って共箱と中身を照合、すなわち正確な鑑定を行うことであり、後者はその鑑定結果を正確に教えてくれることです。希少な品である骨董品を任せるからこそ、鑑定士の腕前と同じように信頼も重視して選ぶ必要があります。
納得のいく鑑定実現のためには?
家に代々伝わってきた家宝の品や自慢の逸品はもちろんですが、所有している骨董品の価値を認めてほしいと感じるのは当然の欲求です。もし鑑定結果に疑問が湧いたり、より詳しくその品物を知りたいと感じた場合は別の鑑定士に新たに鑑定依頼するのも手です。
ただし、品物の真贋・歴史的価値を見定める「鑑定」と市場価値からその業者での買取価格を提示する「査定」を区別し、何を目的に再依頼するのかをきちんと把握しておかないと時間を無駄にする可能性もあります。
まとめ
共箱とそれに記された箱書は単なる収納箱と記録ではなく、中の骨董品の価値を証明し、真贋を見分けるきっかけにもなる重要な品です。コレクションの際には共箱の保管にも注意するのはもちろん、遺品整理などで偶然骨董品を手にした際には箱も一緒に鑑定に出すことを忘れないようにしてください。