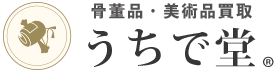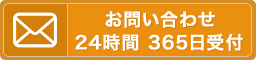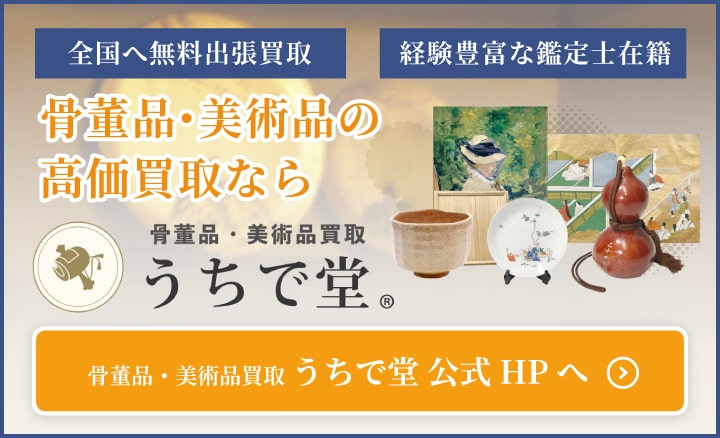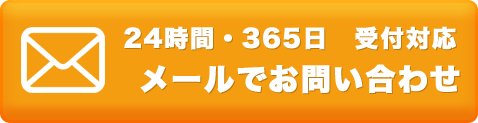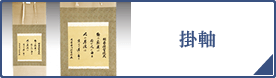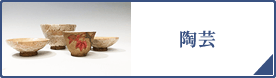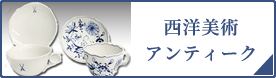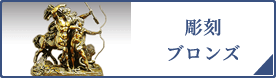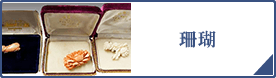骨董品の買取に必要な資格は?個人間での売買の際にも資格は必要?
近年、フリマアプリやECサイトの成長に伴い中古品販売のマーケットも年々増加傾向にあります。皆さんの中にも、ご自身で不要になった品物をフリマアプリで販売した経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一方で自分の持ち物を販売するだけでなく、骨董品などの買取や売買に興味があり、自分でも買取できるお店を持ちたいな……と思っている方も増えてきました。実際にテレビなどでも骨董品鑑定の番組は根強く人気がありますよね。
実は他人から品物を買い取り、販売するにはルールがあります。
そうした中で実際にどうやったら買取ができるのか、資格は必要なのかと疑問に思う方も多いことでしょう。
本コラムでは骨董品の買取に必要な資格や、骨董品鑑定士になるための方法などを詳しくご紹介していきます。
骨董品の買取に必要な資格は?

インターネットの普及により、骨董品の買取は身近な存在になってきました。以前は骨董品買取といえば店舗に持ち込むか、自宅に鑑定士が訪問して査定してもらうなどの方法が主流でしたが、現在はインターネットオークションなどでも売買できるようになりました。
インターネットを通じて簡単に取引できるイメージがありますが、骨董品買取や、店舗運営を行おうと思ったら古物商許可証がなければ買取することはできません。
古物とは「一度使用されたもの」や「新品であっても一度取引されたもの」を指し、これらを売買したりレンタルしたりすることを古物営業といいます。
古物営業を行うためには、古物商許可証が必要になります。
例えば友人から販売目的で骨董品を購入し、インターネットで利益を上乗せして販売する場合も古物商許可証が必要です。
仮に法令違反行為が発覚した場合、罰則が課されることがあり、行政処分の対象になる可能性もありますので、十分に注意が必要です。
古物商許可証の取得方法
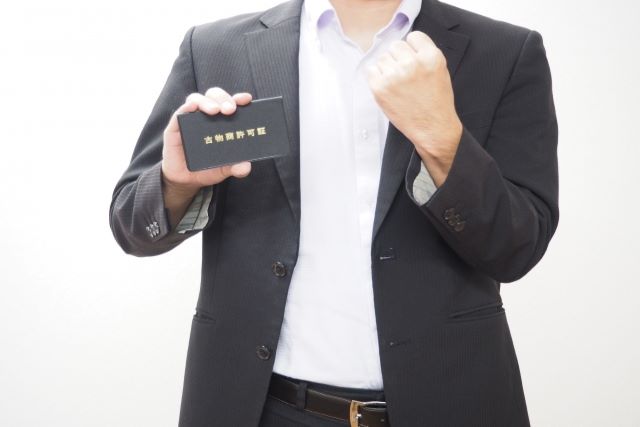
では古物商許可証はどのようにして取得すればいいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
自分で取得する
古物商許可は、古物営業を行う直轄の警察署に届け出を行うことで取得が可能です。
申請書を提出し、添付書類を添えれば申請は可能ですが、申請手続きは非常にややこしく難しいため、知識がない素人が申請を行おうとしてもなかなか受け付けてくれない場合が多いです。古物商許可申請に必要な書類は、申請者の状況によってまちまちで変動することが多いのです。
そのため、時間がかかり結局申請できなかったという可能性も高くなります。
古物商に関して、十分な知識があり時間に余裕のある方でしたら自分で申請してみても良いかもしれません。
行政書士に依頼する
自分で申請を行うことが不安な方は行政書士に申請代行を依頼することもできます。
行政書士は業務内容が多岐に渡っており、官公署に提出する書類の作成や提出の代行を行っておりますが、その種類は1万種類を超えるともいわれています。
そのため、古物商許可を得意とし、専門に扱っている行政書士に依頼をする必要があります。万が一他の分野を専門とする行政書士に依頼してしまうと、時間がかかったり効率の良いサービスを受けられない可能性があるからです。
古物商許可を取得した後も、丁寧にサポートしてくれる行政書士を選択しましょう。
骨董品鑑定士とは?

骨董品鑑定士とは、名前の通り骨董品を鑑定し値付けを行い売買する人のことです。
骨董品売買を行ううえで必要なのは、骨董品の価値を見極めて査定するための専門知識です。鑑定士とも呼ばれることがありますが、品物の市場価値や歴史からその値段を決定する知識を持つ人のことを指します。単純に本物か贋作かを判断するだけでなく、その品物の時代背景や作者についても詳しく知識を有する必要があります。
骨董品鑑定士としての働き方には様々なスタイルがあります。
自分で骨董品店を経営する方もいれば、企業に属して鑑定の仕事を行う方もいます。
バイヤーとして買い付けをメインにすることもあるでしょう。
骨董品鑑定士になるには?

古物商許可証を取得すれば、すぐに骨董品鑑定士として活躍することができるのでしょうか。
実は骨董品鑑定士になるための試験や資格は存在しません。
つまり誰でも「今日から骨董品鑑定士です」と名乗ることができるのです。
しかし骨董品の鑑定は、その品物の歴史や作者、時代風景などを把握し本物の価値を判断しなければならない仕事です。
骨董品の贋作は世の中に大量に出回っており、十分な審美眼と並大抵ではない知識がなければ本物と贋作の見分けすらつかないでしょう。
骨董品に興味を持ち、深く知る努力を積むのはもちろんのこと、細かい部分までしっかりと観察できる力や注意力を磨くことも重要です。
また、ご自身で店舗を持ちたいと考えるなら、お客様に対して接するコミュニケーション能力も磨く必要があります。
経験を積み、審美眼を鍛え、正確な査定ができるようになり始めて骨董品鑑定士と名乗ることができると言っても過言ではありません。
人気の骨董品鑑定士の特徴

人気の骨董品鑑定士にはいくつかの特徴や共通点があります。
買取実績が豊富
買取実績が豊富ということは顧客からの信頼を得ており、かつ多くの骨董品に触れている証拠となります。
骨董品買取は鑑定に関するルールやマニュアルに沿ってのみ行われるものではなく、最終的には鑑定士の目利き力が非常に大事になってきます。
ホームページなどでも簡単に買取実績を調べることができ、豊富な買取実績は安心感に繋がります。
また、利用者の声や口コミなども、鑑定士を選ぶ際にとても参考になる情報です。
専門性がある
骨董品と聞くと陶器や壺を思い浮かべる方も多いかと思いますが、実はそれ以外にも多くの種類を骨董品と呼びます。
【主な骨董品の種類】
美術品
絵画
掛軸
彫刻品
茶道具
陶磁器
刀など
これだけ種類の多い骨董品ですから幅広い種類を取り扱う鑑定士ですと、どうしても一つひとつの骨董品に対する知識が薄くなってしまう可能性もあります。
繰り返しますが、骨董品鑑定はそのものが本物か偽物か判断する能力や知識だけではなく、骨董品が作られた歴史的背景や現在の相場感覚も身に着ける必要があります。
一つの骨董品に対して深い知識がある骨董品鑑定士であれば、適正な価格を見極めることができるでしょう。
出張料金が無料
骨董品鑑定の方法として、自宅や指定の場所まで骨董品鑑定士が出張して鑑定してくれる方法があります。持ち運びができない骨董品や、大量に鑑定を希望する場合は非常に便利な方法です。鑑定士の中にはたとえ現地で売買契約が成立しなくても、出張料金無料でサービスを提供している場合もあります。
骨董品買取を行っている鑑定士は併せて骨董品の販売も行っていることがほとんどですので、良い品物を手に入れるためには出張料金を無料にしてでも鑑定したいという思いがあり、訪問鑑定を無料にしている場合が多いのです。
自分自身では価値を判断できない骨董品も無料で鑑定してもらえるなら安心して依頼できますから、このような鑑定士は人気があります。
まとめ
骨董品買取を行うためには、古物商許可証がなければ買取することはできません。法令違反行為が発覚した場合、罰則が課されることがあるため注意が必要です。
古物商許可証を取得するには、自分で手続きするか、行政書士に依頼するかのどちらかです。古物商許可証を取得すれば鑑定士として活躍できるのかというと、そうではありません。鑑定士になるためには試験や資格が必要ないため、古物商許可の取得後にしっかりと知識と実績を積んで信用を得る必要があります。